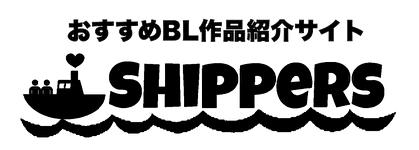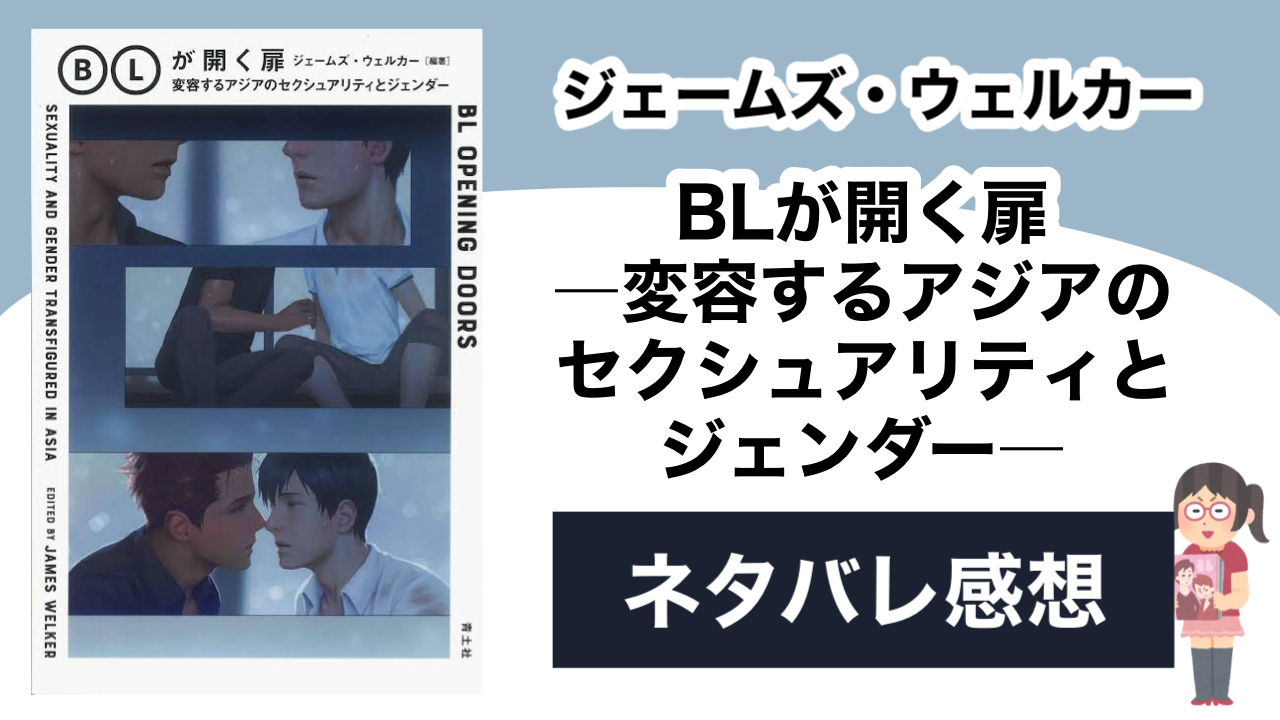中国、韓国、香港、台湾、タイ、インド、インドネシア、そして日本を対象として、とある国際シンポジウムをもとに、アジア諸国におけるBLの変容に関する研究成果をまとめた、ジェームズ・ウェルカー「BLが開く扉―変容するアジアのセクシュアリティとジェンダー―」を読みました!
あらすじ、どんな人にオススメなのかなど、ネタバレ感想とともにがっつりご紹介します!☺️✨
登場人物とあらすじ
 引用:Amazon.co.jp: BLが開く扉 ―変容するアジアのセクシュアリティとジェンダー― : ジェームズ・ウェルカー: 本
引用:Amazon.co.jp: BLが開く扉 ―変容するアジアのセクシュアリティとジェンダー― : ジェームズ・ウェルカー: 本
BLから見るアジアのジェンダー問題の現状 に関するお話。
<あらすじ>
BLはアジアでは独自の変容を遂げ、大きな社会的影響力を持っていた。
BL分析から見えるアジアの現状と日本の特異性――世界のBL、LGBTQ+、マンガ研究の第一人者たちがいま解き明かす。
こんな人におすすめ
- 東アジア各国におけるBLファンダムの歴史をざっくりと知りたい🌏
- 東アジアのBLファンダムとLGBT当事者たちの関係が気になる🤝
- BL作品そのもの・BLファンダムを学術的に捉えてみたい✏️
ネタバレ感想
全14章から成る本作ですが、特に興味を惹かれた章についてのみネタバレ感想を書いていきます。
フェミニズムの時代 、BLの意味を問い直す 2010年代韓国のインターネットにおける脱BL言説をめぐって
この批評では、東アジアでは日本と並んでBLの発祥国と認識されている韓国において、2018年8月頃から主に韓国語ベースのTwitter(現X)において、フェミニズム運動の一環として「BLの消費をやめるべきだ」という言説が主張されていることを明らかにしています。
正直に言うと、長年BL作品をただ読むことに没頭していた私は、フェミニズムとBLが結びつくとは考えたこともありませんでした。たしかにBLを愛する人の割合は女性が多いけれど、BLはあくまで妄想、想像上のものであり、女性に対する現実での差別・不平等との関係性はあまりにもかけ離れて感じられたのです。
「脱BL」は大きく3つのロジックに基づいており、①ゲイとゲイ・セックスに対する嫌悪からの脱BL ②BLの攻め/受け関係は挿入権力を中心にしており、現実の男女における権力関係を膠着化・強化しているという批判 ③男性の表象がメインで女性が排除されるジャンルだという批判 から成っています。
①は例えば「アナルセックスってすごく汚いんだよ。挿入するちんこにうんちがついたりするんだよ!」といった批判で、私はあまりぴんときませんでした。
というのも、BLはゲイの人々の恋愛を描いているのであり、ゲイの人々は実在しています。彼らがいるからこそBLが成り立つのであって、BLを深く愛する人ほど、ゲイやゲイ・セックスへの嫌悪という気持ちは生まれづらいのではと感じました。嫌悪感を感じて脱BLした人々は、BLは完全に架空の関係性だと思っているのでしょうか?
②はBLの攻め=男性、受け=女性とみなし、挿入する側が挿入される側を性行為という暴力によって支配しているこの状態は、男性が女性を支配している現実を支持するのと同義になっている、という批判です。
これは後で紹介する章で反論がなされていますが、BLにおいて攻めが受けに挿入をするのは事実ですが、だからといって権力関係がすなわち攻め>受けになるわけではないんですよね。「惚れた方が負け」という言葉がありますが、何もかもを持っているスパダリ攻めの方が、何も持っていない受けに対して激しい執着心を抱いている…という構図は、BLではお馴染みです。むしろ、BLは男同士かつ恋愛の話だからこそ、そういった権力関係から解き放たれていると考えられます。
③は、BLは終始男性の物語であり、女性が排除されていることから、女性ナラティブ(の物語)ではない=男性、特にゲイへの憧れを強めさせるという批判です。
BLそのものがゲイ男性を性的消費していることから、女性ナラティブであると私は思います。なので、作中に女性キャラクターが登場しなかったり、女性キャラクターが露悪的に描かれていたからといって、BL=ゲイ男性を賞賛している、女性にとって悪だ、とは思いません。
脱BLは刺激的な言説であるとは感じましたが、自分はあまり共感できませんでした。脱BLのベースには、ミサンドリーがあるような気がしています。確かに現実で我々女性は男性から抑圧されていますが、だからといって男性、ゲイ男性を娯楽の中からも締め出すのは、逆に女性差別からの逃避なのではと感じてしまいました。フェミニズムの理想を実現したいのならば、間違いなく男性の応援が必要です。嫌悪し排除するのではなく、誰と手を携えてよりよく社会を変えていけるのかを模索したいと自分は感じました。
ゲイファンのファン 想像と存在の間から立ち上がるタイのボーイズラブ
タイといえば…「BLドラマ」!と、身の回りの腐女子たちが口を揃えて言うようになったのは、かの有名なタイBLドラマ「2gether」が、2020年に放送されるなりアジア全土で大ヒットを記録してからだと思います。「2gether」以降もタイBLドラマは快進撃を続けており、BLドラマの主役カップルを演じた俳優さんたちが日本や中国、韓国でファンミーティングを頻繁に開くなど、ワールドワイドにその魅力が知られています。
さらにはそのようなBLジャンルの盛り上がりによって議論が活性化したのか、タイでは2025年1月23日から同性婚が合法化。東南アジアではタイが初めての例となりました。
日本では、ゲイと腐女子の間には高い壁があるように私は感じています。それゆえに、タイではなぜBLという、いわゆる「ファンタジーなゲイ・ロマンス」を愛する腐女子たちが、現実のゲイたちと手を取り合い、社会に良い影響を及ぼせたのかを知りたいと思いました。その理解のために、大きな助けとなったのが本章です。
本章では、タイの腐女子たちがどんな風にBL作品を楽しんでいるのか、さらに、タイのゲイたちはそんな腐女子たちの動きを受けてどのように変化しているのかを詳しく説明してくれます。
一番興味深かったのは、タイのリアルなゲイカップルたちが、腐女子たちからの人気を受けて、いわゆるBLの美的様式を体現しようと積極的に動いていることです。
日本でも若くフェミニンなゲイカップルが、YouTubeや Instagramなどで活動していますが、日本の腐女子たちは、タイの腐女子たちが母国のゲイカップルたちを支持するほどには、熱狂していないように感じます。
日本の腐女子たちは、タイの腐女子たちほど「ナマモノ」(現実のゲイカップル)への欲望が高くないのかもしれません。逆に言えば、なぜタイの腐女子はこれほどまでに「リアルなゲイ」たちに「理想的なBL仕草」を求めるのでしょうか?本章ではそこまでは言及されていませんでしたが、気になるところです。
ただ、タイにおいてもマスキュリンなゲイ男性たちは多数います。彼らはBL的イメージを積極的に拒否していますが、「BL人気はおそらくタイ社会において、現実上の同性愛に対する寛容性の向上に貢献している」と著者は書いています。
日本もタイも家父長制的、ゲイフォビア的な社会的風潮はさほど変わらないと思っていたのですが、日本ではマスキュリンなゲイ男性たちの声がとりわけ大きく聞こえるように感じます。もしくは、タイでは腐女子たちが彼らの声を上回るほどに、ゲイのロマンスを現実上でも想像上でも強く支持をしたということなのでしょうか。
一腐女子としては、タイでのBLブームが一時的なものに留まらず、同性婚の合法化という形で社会にまで素晴らしい影響を及ぼしたことは、とても眩しく、ぜひ日本もその後を追いたい!そのために自分は何ができるだろうかと考えさせられました。
ラブ&エロの「やさしい世界」のクィアな欲望
私は10代でBLに出会い、それからはずっとその時々で情熱の高低はあれど20年近くこのジャンルを愛し続けてきました。
ただ、なぜ自分がヘテロの恋愛物語に居心地の悪さを感じ、BLではそれを感じないのか。なぜBLでの恋愛や性愛の描写はすんなりと、しかもどこか清々しくさえ感じるのか。そういった疑問を感じながらも、それ以上に問いを深めることができずにいました。
本章では、腐女子の人々のそういった「なぜ私はBLがこれほど好きなのだろう?」という疑問に正面から答えてくれています。
BLはヘテロノーマティリティ(異性愛が当たり前という社会規範)が蔓延するジェンダー秩序への抵抗であり、現実の女性差別との戦いの一つであると筆者は語ります。
また、腐女子たちは「愛されるファンタジーとして受けに自己を投影している」というだけではなく、「性差別のある社会で抑圧される地位にある女性たちが、人として対等に向き合える場として、権力構造を転じさせることのできる恋愛という設定を選んだ」と考えられるとも語っています。
これは長年自分のことながら理解できていなかった、「なぜ私はBLを愛するのか」の答えだと感じました。
30年近く女性として生きてきた私の感覚として、日本では「女に生まれて良かった」よりも「女でなければこんな嫌な思いをしたくて済んだのに」と辛く思うことの方が圧倒的に多いです。
特に私が九州の田舎出身というのもありますが、圧倒的な男性優位社会、根強い家父長制、ミソジニー、そして当然のように行われるあらゆる女性の性的消費…まだ齢一桁の頃から、ヘテロ男性たちの無自覚で傲慢なこれらの行いや考えに振り回され、私は10代にして、女性として生きることに疲れ果てていました。恋愛に夢中になる同世代を横目に、そんなものの何がいいのかと膿んだ気持ちを持て余していました。
そんな時に出会ったのが、BLです。BLの中では、男性だから、女性だから、優位に立つという考え方はありません。攻めも受けも、互いにどんな社会的立場であっても、恋愛という土俵の上で平等です。どちらかがいつも一方的に性的消費されたり、暴力、妊娠や出産の不安に怯えたりすることもありません。きっと私にとって、BL作品の中の恋愛は、理想の恋愛だったのだと思います。こんなふうに、平等に人として恋がしたいと願ったからこそ、これほど長い間このジャンルを愛してきたのだと思います。
また、 「BLが男性同士の恋愛をテーマに描き、拡散し続けていることは、同時に、社会的・政治的多元主義を支持する政治的表明となり、それは社会秩序や体制に対する脅威となると言えるだろう」とも筆者は語っており、私はこの言葉に強く励まされました。
BLを愛するということは何の役にも立たないような、役に立つ趣味でなければ人前で堂々とは話せないような、そんな自虐的な気持ちで、BLを愛していることを隠し続けてきたからです。
でも、BLを愛することが社会的・政治的多元主義を支持する政治的表明となるならば、自分たちの存在は性的マイノリティーの人々を勇気づけることができるのかもしれない、自分がBLを愛する心は決して恥ずかしいものではないと思えたのです。
最後に、本章で最も感銘を受けた文章を引用します。
ロマンティックなラブとエロでできた現在のBLは自分の存在がそのままで認められ、傷ついても立ち上がることができるよう恋する2人が幸せになれるよう、周囲の人々が応援してくれるやさしい世界だ。そこではラブに終始し、LGBTQの問題を捉えない作品も多い。政治的に正しくないとされるようなBLも、またクィアな欲望とリンクし、ジェンダーとセクシュアリティーにおいて、周縁化(社会の主流から外れた人々や集団が、政治的、経済的、文化的な影響力を持つ機会を制限される状態)された人々が生き延びるためのやさしい世界として存在しているのだ。(中略)
BLを正しさだけで論じるのではなく、混沌とした世界で描かれる多様な生と性のナラティブをクィアな欲望と位置づけ、そこから差別を捉え直す抵抗方法もまた必要だと考える。
簡単に言えば「どんなBL作品をも多様な欲望として受け入れて、差別を改めて捉え直そう」ということなのですが、自分の中でのBLの捉え方や意識が、この文章を読んで少し変わりました。
ただBLを娯楽として消費するのもいいけれど、その一歩先も考えたいと思うようになったんです。BLを通して、性的マイノリティーや女性が差別されている現状を見つめ直したり、差別に立ち向かう勇気をもらったり、もっと自分から「苦しい」と感じている現状を打破するために動こうと思えるようになりました。
BLは、私の力の源です。BLに生きる元気と勇気をもらってきました。これからもBLを愛し、楽しみ続けられるように、自分にできることを考えて行動したいです。
まとめ
BLの起源と言われる日本・韓国を始めとして、タイ・中国・台湾・インドネシア・インド…といった、東アジアのさまざまな国々におけるBLの現在(と言っても、本作が刊行されたのは2019年10月なので、それ以前の状況だと思うのですが)を知られて、とても勉強になりました。
電子書籍がないので電子派には少し購入のハードルが高いかもしれませんが、本作のように東アジアのBLの状況を網羅的に批評した書籍はほとんど見かけないので、BLを愛する者の基礎知識・前提知識として本作を持っておくと良いよ〜と、私はおすすめしたいです☺️✨
本作はBLの歴史を知られるだけでなく、なぜ自分がBLを好きなのか分からない腐女子にとっても、読みながら自分を見つめ直す良い機会になると感じました。
さまざまな国のさまざまな腐女子が登場し、彼女たちの考え方が理論的に露わになるので、自分はBLの何にときめいているのか、何に嫌悪を感じるのか、BLを読んでどうしたいのか、を自然と考えさせられます。
BLを愛する誰もが一度立ち止まって、自分自身について考えることができる良い一冊でした📚✨