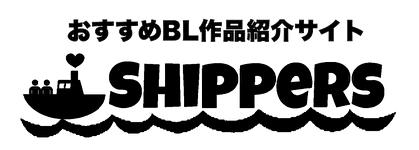さとむら緑先生「雨は悄然と降っている」のネタバレ感想です。
これまで出会ったBL小説の中でも、マイベスト5に入る素晴らしい作品でした。
BL小説好きなら、絶対絶対一度は読んでほしい名作です。
登場人物とあらすじ
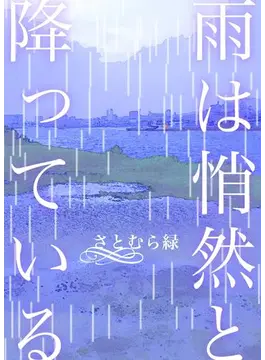
無口な作家×お調子者の会社員 元高校同級生、親友同士のお話。
<あらすじ>
婚約者に家を追い出され、途方に暮れていた雄一朗(受け)は偶然、同級生で小説家になった守屋要(攻め)と再会する。
渡りに船、とばかりに守屋の家に転がり込み、そのまま居候生活を始めた雄一朗。
だが、何事にも無関心に生きている守屋を知り、いつしか昔のように彼から必要とされたいと思うようになって…。
こういう人におすすめ
- 丁寧な心理描写・情景描写が好き
- 純文学、文芸作品が好き
- 平凡な日常から、ふと非日常が始まるようなお話が好き
ネタバレ感想
①映画のように美しい情景にうっとり

本作はさとむら緑先生の文庫デビュー作なのですが、デビュー作とは思えぬほど、いや、だからこそなのか、さとむら先生の瑞々しい感性がこれでもかと特に地の文に発揮されています。
主人公・三島雄一朗(受け)は彼女と喧嘩をして、偶然会った高校時代の親友である守屋要の家に転がり込みます。
守屋はどうやら雨男で、彼の行く先々で雨が降ります。三島の記憶の中の守屋もいつも雨の中におり、守屋=雨という構図がはっきり見えるのですが、たびたび描かれるこの雨のシーンが毎回とても美しいんです。
簡単に言えば「雨が降っている」。ただそれだけの天気なのに、その雨がどんな音を鳴らしているのか、雨が連れてきた湿気がどんな気持ちにさせるのか、雨を感じてそのキャラクターはどんな気持ちになっているのか…が毎回丁寧に描かれているので、同じ雨のシーンでも、全く飽きることがありません。
しかも雨と聞けば、多くの人が「曇り空」で「色彩のない」「冷たい」情景をイメージすると思うのですが、これがさとむら先生の描写力のすごいところで、雨の日なのにむしろくっきりと、いきいきと、描写されているものたちの色が、私たち読者には伝わってくるんです。
さとむら先生の描く雨の日は、なぜかそこに息づく植物や動物、なんということもない無機質な建物たちまでもがそれぞれのストーリーを持って息づいていると感じさせられます。
それは読めば読むほど感じるもので、ぜひあなたにもそれを実際に読んでみて体感してほしいです。
②はっきりしないからこそ生々しい。リアルに息づく男たちの恋

三島には2歳年下の病気の妹がおり、彼は長年彼女を生かすために自分は生きているのだという責任感で生きていました。やがて彼女は亡くなってしまうのですが、三島は長年妹を喜ばせようとそればかり考えて生きてきたせいか、「誰かの役に立つ自分でなければ存在意義がない」と感じるようになってしまいます。
彼女と喧嘩した理由も、「三島さんにしか相談できないんです」と女性社員に恋愛相談を持ちかけられて一晩中愚痴を聞いてやったから。そして三島は彼女と喧嘩して見限られてしまうと、次は守屋に求められたいと行動するようになります。
長年三島に叶わぬ片思いをしていた守屋からすればたまったものではありませんが、三島にとっては「求められること」即ち「生きる意味をもらうこと」なので死活問題なんですね。
彼女と喧嘩をしている間に、守屋とほぼ恋人のような関係に陥っていく三島。
本来であればこういったあやふやな関係は推奨されるべきではないとは思いますが、とはいえ、人間というのは非合理的な生き物。三島なりの理論では一応筋の通った言動をしているのですが、側からみればそれは不道徳な関係にも見えて…。
このあやふやな関係を後押しする要素として、三島がノンケであることも挙げられます。守屋はバイですが、三島は完全なノンケ。それゆえに守屋と密接に触れ合いながらも、それ以上にはいけないと無意識のブレーキがかかっているようでした。
この無自覚にどっちつかずな三島の言動にやきもきさせられるも、だからこそ他人の恋愛話って面白いんだよな…と思わされます。
③自分を偽り生きてきた二人だからこそ、分かり合える

守屋は学生時代にたった一人の親友だと思っていた相手から喫煙疑惑を押し付けられた経験から人を信じられなくなり、長い間人に心を開かずに生きてきました。しかし心の底では人を愛したい、信じたいと渇望しており、自分に好意を持ってくれる人の愛を信じたいと思いながらも、裏切られるのを恐れるあまりに、相手の好意を否定し続けていました。
一方、三島も妹のためにわざと道化役を進んで演じていたため、それが板についてしまい、誰の前でも本当の自分を出すことができなくなってしまいます。本当の三島は、例えば妹のように求めてくれる存在がいなければ自分の存在意義はないと思うくらい、他者からの求めに依存しているのですが、普段はそれを悟られないように何重にも仮面をかぶってその自分を隠し続けています。
守屋も三島もおたがいに本当の自分を他人に見せないように覆い隠して生きており、だからこそ、一見正反対の性格に見えても実は分かり合えるのだと思います。
まとめ
彼女と喧嘩をして家を追い出された会社員の三島は、偶然にも高校時代の親友である守屋に出会い、しばらく居候させてもらうことに。思ったよりも長い居候生活の中で、二人の気持ちは変化していき…。
文章力に定評のあるさとむら緑先生の、鮮烈な文庫デビュー作です。処女作ということもあり、鋭くも鮮やかな描写力のみすみずしさが光ります。特に地の文の匂い立つような美しさは類を見ず、まさに唯一無二の素晴らしさと言えるでしょう。
互いに深い心の傷を抱えた守屋と三島が、11年ぶりに再会し、ともに暮らす中で、徐々に心を開き、自然と傷を癒していく姿には、まるで手負いの獣を懐かせていくような緊張感と感動があります。
アート系の映画が好きな方、詩のように美しい小説を読みたい方、文芸作品が好きな方などに特におすすめしたい一冊です。
雨音を聞きながら、ぜひじっくりと読んでみてほしいです☔️✨